現場でよく聞かれた“葬儀の見積もり”とその考え方
「お葬式って、いざという時、何から始めたらいいのかわからない…」
「生前に準備をしておきたいけど、見積もりってどうやって取るの?」
そんな疑問を抱えて、葬儀社を訪れる方はとても多くいらっしゃいました。
私が現場で葬祭ディレクターとして仕事をしていた頃も、
ふらっと相談に来られて、「何から手を付ければいいのか教えてほしい」とおっしゃる方、
「費用の目安を知りたいだけなんだけど…」という方が本当にたくさんいました。
この記事では、そんな経験をもとに、
お葬式の準備をする上で必要なこと、そして見積もりの取り方や考え方を、わかりやすくまとめてお伝えします。
地域性もありますので、参考程度に…
■ そもそも「準備」って何をするの?
よくある誤解が、「お葬式の準備=契約」だと思ってしまうこと。
でも実際には、「いざという時に困らないように、情報を整理しておく」ことこそが、いちばんの準備です。
準備として整理しておくと安心なこと
- 希望する葬儀の形式(宗教・規模・会場)
仏式か神式か、無宗教か。家族葬がいいのか一般葬なのか…など。 - 菩提寺の有無とお付き合い
菩提寺がある場合は、宗派や連絡先を確認。戒名のことも含めて話しておくとスムーズ。 - 家族の意向・希望(誰を呼ぶか、場所の希望など)
「身内だけで静かに送ってほしい」「お世話になった人には声をかけたい」など。 - 費用の目安を知る
予算をざっくり把握し、無理のない形を考える。 - 万が一の際の連絡先や対応窓口を明確に
「亡くなったら、どこに電話すればいいのか」──実はここを知らない人が多いです。
■ 「費用の見積もりを知りたい」だけでも大丈夫
私が担当していた頃も、「見積もりだけでもいいですか?」と遠慮がちに来られる方が多くいました。
もちろん、大歓迎です。
見積もりを取るときにお伝えするとよいこと
- どんな形式を考えているか(家族葬・一般葬・一日葬など)
- 火葬場の場所やお住まいの地域(火葬場利用料は自治体で異なります)
- 宗教の有無(僧侶の手配が必要かどうか)
- 想定人数(会葬者の人数で、会場・返礼品・料理の量が変わります)
これらがある程度わかっていると、より具体的な金額が出しやすくなります。
ただ、最初はわからないことだらけで当然です。
「だいたい〇〇万円以内で収めたい」と希望だけ伝える形でもOK。
葬儀社側もその枠内で可能な提案をしてくれるはずです。
■ 葬儀の費用はどうなっている?
葬儀の費用は大きく3つに分けられます。
- 葬儀基本費用
祭壇・棺・安置・搬送・スタッフ・式場使用料など。 - 実費費用
火葬料、式場使用料(自治体や斎場によって異なる)、遺影、貸衣装など。 - 接待費用
通夜ぶるまい、精進落とし、返礼品など人数に応じて変動。
加えて、宗教者へのお礼(お布施・玉串料など)もありますが、これは直接お寺や教会との関係で変わる部分です。
● 実際に見積もりを出すと…
同じ家族葬でも、シンプルに火葬のみで済ませるプランなら20万円〜
通夜・告別式を含むしっかりとした家族葬であれば60万円〜
さらに会葬者が多くなれば100万円を超えるケースもあります。
ここで大切なのは、「高いか安いか」ではなく「納得できる内容かどうか」だと思います。
■ 見積もりは“比較”していいもの
葬儀社によってプランや考え方が異なるため、
必ず2社〜3社ほど比べてみることをおすすめします。
比較のポイント
- プラン内容が明確か?(何が含まれていて、何が別料金か)
- 担当者が誠実に対応してくれるか?
- 急な変更に柔軟に対応してくれそうか?
- 「押し売り」や「不安をあおるような説明」がないか?
見積もりの時点で「この人になら任せても大丈夫そう」と感じられるかどうかも、
とても大切な判断材料になります。
■ 事前相談をしておくと、本当に安心
実際に私が対応していた中でも、
事前に相談に来ていたご家族は、いざという時にとても落ち着いて対応されていました。
なぜなら、「やることがわかっている」という安心感があるから。
ご逝去の連絡 → 搬送 → 安置 → 葬儀日程の調整 及び 打ち合わせ
この流れをあらかじめ説明してもらっているだけで、心の余裕がまったく違ってきます。
■ 最後に|“葬儀の準備”は、「備える」というやさしさ
葬儀の準備というと、なんだか縁起でもないことのように感じるかもしれません。
でも、本当は逆で、「大切な人に迷惑をかけないように」という想いから始まる“思いやり”なのです。
- 自分のため
- 家族のため
- 残された人が困らないために
準備をするという行為は、葬儀そのものを“良いもの”にするためではなく、
「安心して見送れるようにするため」にあるのだと、私は現場で日々感じていました。
最初にもお伝えしましたが、地域の特性などもあります。
ぜひ、「ちょっとだけ話を聞いてみようかな」という気持ちで、
お近くの葬儀社に気軽に相談してみてください。
また、個人的に働いていて、ご葬儀の相談の時にお困りになっていたのは、写真です!
私自身もそうですが、なかなか大人になって写真を撮らなくなったこともありますし、
最近だと、コロナなどでマスクをしているお写真しかないなどもあります。
葬儀会社にもよるかもしれませんが、デジタル写真(スマホやUSB・SDカード)のもとで作れたりもするので、準備をする上でそういうものもご準備されるとよろしいかなと思います。
このブログでも、気になることがあればいつでもコメントやメッセージでご相談くださいね。
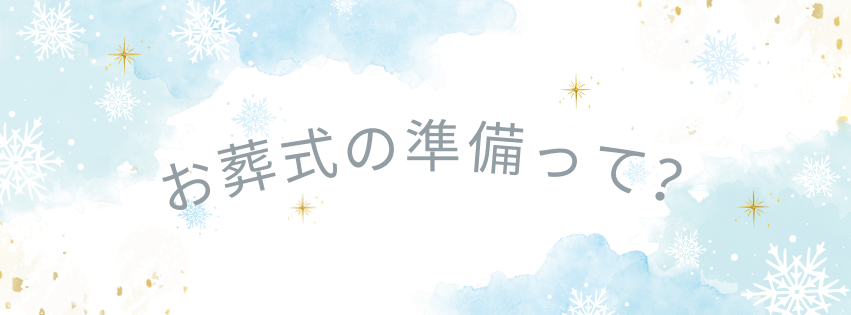
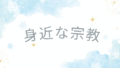
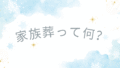
コメント