お葬式に参列した際にいただく「香典返し」。
いただく側も贈る側も、実はちゃんとしたルールや意味があることをご存じですか?
今回は、香典返しの意味・時期・相場・品物選びのコツなど、意外と知らない豆知識をわかりやすくご紹介します。
◼ 香典返しって何のためにあるの?
「香典返し」とは、葬儀や法要で香典をいただいた方に対し、感謝の気持ちを込めて贈るお礼の品です。
本来は仏教の「四十九日法要」などの節目において、故人の供養の一環として贈られるもので、
「無事に忌明けを迎えました。ありがとうございました。」
という意味が込められています。
そのため、香典返しは「慶事の引き出物」とは違い、あくまで「丁寧なお礼」が基本です。
◼ 香典返しの時期:いつ贈るのが正解?
香典返しは、宗教や地域の風習により異なりますが、一般的には四十九日明けに贈るのが基本です。
◆ 仏教
四十九日(忌明け)を終えてから1週間以内が目安。
この時期に「挨拶状」とともに郵送で送るのが一般的です。
◆ 神道
五十日祭のあとに「偲び草(しのびぐさ)」として贈ることが多いです。
◆ キリスト教
1ヵ月後の追悼ミサ後や、召天記念日を目安に贈ります。
◆ 即日返し(当日返し)って?
最近では、葬儀当日に会葬御礼とセットで**「即日返し」として渡すスタイルも増えています。
これは、遺族の手間を減らす意味でも合理的な方法ですが、香典の金額によっては後日追加で返礼品を送る**こともあります。
◼ 香典返しの相場:いくらくらいがちょうどいい?
香典返しの金額は、一般的に**いただいた香典の「半額〜1/3程度」**が目安です。
| 香典の額 | 香典返しの目安 |
|---|---|
| 3,000円 | 1,000円前後 |
| 5,000円 | 2,000〜2,500円 |
| 10,000円 | 3,000〜5,000円 |
あまりに高価な品を贈ってしまうと、かえって相手に気を使わせてしまうことも。
「高すぎず・安すぎず・実用的」が選ぶコツです。
◼ 香典返しにふさわしい品物とは?
香典返しの品物には、「消えもの(=使えば無くなるもの)」が好まれます。これは「悲しみを残さない」という意味も含まれているからです。
▼ よく選ばれる香典返しの品
- お茶・海苔・コーヒー
- 和菓子・洋菓子の詰め合わせ
- 洗剤やタオルなどの日用品
- カタログギフト(最近人気)
中でも**「消耗品+挨拶状+包装」**がセットになった贈答品は、選びやすく、もらっても使いやすいと喜ばれます。
◼ 挨拶状にはどんなことを書く?
香典返しと一緒に添える「挨拶状」は、品物以上に大切です。
お礼の気持ちを丁寧な言葉で表現し、相手への感謝を伝えましょう。
一般的な挨拶状の例(仏教)
拝啓
このたびは 亡き○○の葬儀に際しまして
ご厚志を賜り 心より御礼申し上げます
おかげさまで忌明けの法要も滞りなく相済みました
つきましては 心ばかりの品をお届けいたします
ご笑納いただければ幸いに存じます
略儀ながら 書中にて御礼申し上げます
敬具
宗教や地域によって若干の表現が異なることもあるため、文例集や贈答の専門業者のテンプレートを参考にするのもよいでしょう。
◼ 香典返しの豆知識【まとめ】
| 豆知識 | 内容 |
|---|---|
| 即日返しは増加中 | 葬儀の当日に返礼品を渡すスタイルが主流になりつつある |
| 高価すぎる返しは逆効果 | 「半返し」が原則。高額すぎると相手に負担をかけてしまう |
| カタログギフトが人気 | 好みを問わず贈りやすく、相手も選べる楽しさがある |
| 宗教ごとに表現を使い分ける | 仏教とキリスト教で挨拶状や名目が異なるため注意 |
◼ 最後に:香典返しは「心」を届ける贈り物
香典返しは、形式的な儀礼ではなく、**お世話になった方へ感謝を伝えるための“贈り物”**です。
贈る側の想いが伝わるよう、品物選びや挨拶状の言葉にも心を込めたいですね。
特に近年では形式にとらわれすぎず、柔軟に対応するスタイルも増えています。
迷ったときは、専門店や葬儀社、地域のしきたりをよく知る人に相談するのもおすすめです。

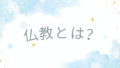
コメント