法要やお供えの場面で贈る品物には、相手に対する感謝や敬意の気持ちが込められています。
特に法要では、参列していただいた方やご住職へのお礼として贈り物を用意することが一般的です。
この記事では、法要やお供えの贈り物選びのポイントとマナーについて、わかりやすく解説します。
法要のお返しとしての「引き物」とは?
法要に参列いただいた方へお渡しする品物は「引き物」や「法要返礼品」とも呼ばれます。香典返しとは異なり、当日その場で手渡しするのが一般的です。内容としては、日常的に使える消耗品や、重すぎず持ち帰りやすいものが好まれます。
代表的な引き物の例:
- 焼き菓子や羊羹などの菓子類
- お茶・コーヒーセット
- タオルや洗剤などの日用品
- カタログギフト(軽めの価格帯)
価格帯は1,000円~3,000円程度が目安です。ただし、地域によって慣習が異なることもあるため、事前に確認すると安心です。
ご住職へのお礼「御膳料」「お布施」との違い
僧侶に対してお礼として包む金品には、いくつかの名称があります。混同しがちですが、意味や目的が異なります。
- お布施:読経などの宗教的な行為への謝礼。金額は宗派や地域により異なるが、3万円〜5万円が一般的。
- 御膳料:食事をお出しできない場合に渡す食事代の代替。5千円〜1万円程度。
- お車代:遠方から来てもらった場合の交通費。こちらも5千円〜1万円程度が目安。
これらをそれぞれ別封筒に包み、法要当日に手渡しするのが丁寧な対応です。
お供えとしての贈り物選び
お供え物を贈る場合は、宗教・宗派や地域の習慣を配慮することが大切です。一般的に避けられるものや選ばれる定番の品を知っておくと、安心して贈ることができます。
避けた方がよい例:
- 肉や魚など生もの(仏教では「殺生」を連想させる)
- 匂いの強い食品
- 商品券(法要のお供えとしては不適切)
おすすめのお供え物:
- 菓子類(小分け包装のもの)
- 果物(盛り合わせ、フルーツ缶)
- 線香やろうそくの詰め合わせ
- 日持ちする食品(乾物や海苔など)
包装は地味めの色合いで「のし紙(掛け紙)」をかけ、表書きには「御供」「粗供養」などと記載します。
時期に応じた贈り物の工夫
命日から日が経った場合や、初盆・一周忌など節目の法要では、季節に応じた品物を選ぶことで、より心のこもった印象になります。
季節に合った品の例:
- 夏:涼しげなゼリー、水ようかん、冷茶セット
- 冬:カイロ付きの実用品、おしるこ、温かい飲み物セット
時期や気温、相手の家族構成などを考慮して贈り物を選ぶと、思いやりがより伝わるでしょう。
贈るときのマナーと注意点
- のし紙は「黒白」または「双銀」の水引を使用(関西では黄白の場合も)
- 表書きには「御供」「志」などを使用し、名前を下部に記載
- 持参する際は紙袋に入れ、訪問時に袋から出して手渡すのが基本
- 宗派によってタブーとされる品があるため、事前確認が大切
まとめ
法要やお供えの贈り物には、形式やマナーだけでなく、相手への思いやりや気遣いが込められています。形式にとらわれすぎず、相手の状況や心情を汲み取って選ぶことが何より大切です。この記事を参考に、感謝の気持ちをしっかりと届けられる贈り物を選んでみてください。



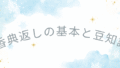
コメント