日本の葬儀文化や宗教行事では、服装や持ち物に対するマナーが細かく定められていることが多く、「知らなかった」では済まされない場面も少なくありません。
この記事では、特に気を付けたい法事や弔問のときの服装と手土産について、基本から実践的な選び方まで詳しく解説します。
失礼のない対応ができるよう、ぜひ参考にしてください。
法事・弔問時の服装マナー:場面と関係性で異なる選び方
法事での基本的な服装
法事とは、故人の供養を目的として行われる仏教行事です。代表的なものには四十九日、1周忌、3回忌などがあります。
服装の基本は「略式喪服」や「準喪服」。黒を基調とした落ち着いた装いで、派手さを避けるのが原則です。
- 男性の場合:黒や濃紺のスーツ、白いワイシャツ、黒ネクタイ、黒の革靴が一般的。
- 女性の場合:黒や紺のワンピースやアンサンブル。肌の露出を控え、ストッキングは黒、靴も黒で光沢のないものを選びましょう。
なお、法事が自宅で行われる場合や、家族だけの簡素な形式であれば、ダークグレーなどの地味な服装でも問題ありません。
ただし、遺族や喪主との関係が深い場合は、しっかりと準喪服を着用するのが望ましいです。
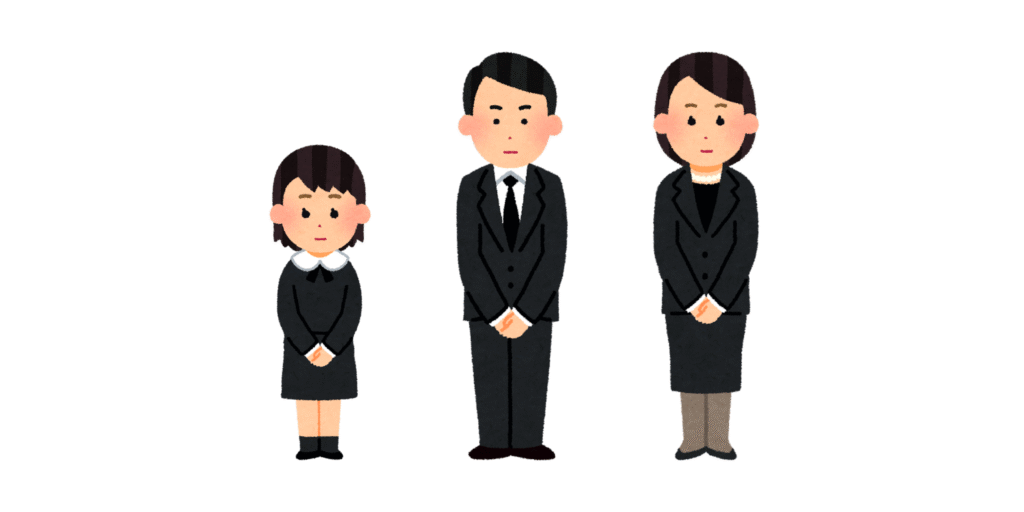
弔問時の服装:平服とは?
通夜や葬儀以外で故人の家を訪れる「弔問」では、喪服を着る必要はありません。とはいえ、あまりにカジュアルな服装は避けましょう。
- 「平服」と指定があれば、暗めの色のシャツにジャケットや、無地のワンピースなどが適切です。
- 派手なアクセサリー、露出の多い服、ジーンズやスニーカーは控えましょう。
【関連記事】 👉 最近の葬儀の服装って?
手土産のマナー:何を持っていけばいい?
法事のお供え・手土産
法事に参加する際には、仏壇に供える「お供え物」や、遺族に対する「手土産」を用意するのが一般的です。
- 定番のお供え物:果物、お菓子(個包装の焼き菓子や和菓子)、お線香、花など。
- 避けるべきもの:肉類、魚介類、香りの強いもの、保存性の悪いもの。
お供えはのし紙をつけ、「御供」または「御仏前」と表書きし、水引は白黒または双銀の結び切りが適切です。詳細は下記のページを参考にしてください。
【関連記事】 👉 熨斗(のし)の意味と種類:使い分け完全ガイド
弔問時の手土産
弔問時に手土産を持参する場合、あまり仰々しくならないように、控えめで心のこもったものを選びます。
- 選ばれる手土産:焼き菓子の詰め合わせ、タオルセット、線香、お茶。
- 表書きと水引:「御供」または「志」とし、簡易ののしをつけても良い。
相手の宗教が仏教以外の場合は、表書きに注意が必要です。たとえば、神道では「御神前」、キリスト教では「お花料」など、適切な表現があります。詳しくは以下の記事で解説しています。
【関連記事】 👉 香典袋の正しい書き方
よくあるマナー違反と避け方
NG例1:カジュアルすぎる服装
親しい間柄でも、ジーンズやキャラクター柄の服、派手なアクセサリーはNG。シンプルで落ち着いた装いを選びましょう。
NG例2:包装や表書きが不適切
コンビニ袋やブランドロゴ入りの紙袋などで持参すると印象を損ないます。無地の袋か、仏事用の手提げ袋に入れるのが基本です。のしの表書きが「御霊前」や「御仏前」など、宗教やタイミングに合っていないケースも要注意。
【関連記事】 👉 香典袋の表書きの選び方:御霊前?御仏前?
おわりに:マナーは相手を思う気持ちの表れ
服装や手土産のマナーは、形式やルールのように見えて、実は「相手を思いやる心」が最も大切です。「こうするのが正解」と固く考えるよりも、「これで失礼に当たらないか」「気を使わせないか」と配慮することで、自然とふさわしい行動がとれるようになります。
こうしたマナーを知っておくことは、急な場面でも慌てずに対応できる備えにもなります。終活や贈答マナーの一環として、今から少しずつ知識を深めておくことをおすすめします。
【関連リンク集】

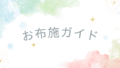
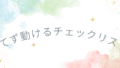
コメント