お布施の金額、渡し方、タイミングまで徹底解説
「お布施って、いくら渡すの?」「いつ、どうやって渡せばいいの?」「そもそも“お布施”って何?」
仏事や法要の場面で避けて通れない“お布施”について、多くの方が疑問や不安を抱えていらっしゃいます。
この記事では、葬儀・法事・お盆などの場面で必要となるお布施について、基本的な考え方から、金額の相場、封筒の書き方、渡し方までをわかりやすく解説します。
お布施とは? ― お寺への“感謝”を表す心
お布施とは、僧侶に対して読経や供養をしていただいたことへの感謝の気持ちを「お金」という形で表したものです。
仏教の考えでは、お布施は本来「見返りを求めずに施す行い(布施行)」の一つとされています。
つまり、価格や物品の対価ではなく、あくまで「気持ち」です。
ただし、現代では「感謝の気持ちだけでいい」とはいっても、社会的慣習としてある程度の相場や形式が存在するため、実際にはそれに沿って渡すことが多くなっています。
お布施が必要な場面とは?
お布施は、以下のような仏事の場面で必要になります。
- 葬儀(通夜・葬式・初七日など)
- 法事(四十九日、一周忌、三回忌など)
- 納骨・開眼法要(お墓や仏壇を拝むとき)
- お盆・お彼岸(僧侶を自宅に招くとき)
- 戒名をいただくとき
- 年間の「お年玉」的な布施(寺院への年末年始の御礼)
それぞれの場面で、金額や渡し方が多少異なるため、以下で詳しく説明していきます。
お布施の金額相場は?
お布施に「これが正解」という金額はありませんが、一般的な相場は以下の通りです。
| 仏事の種類 | お布施の相場(目安) |
|---|---|
| 通夜・葬儀 | 20万〜50万円(戒名料含む) |
| 初七日・四十九日 | 3万〜5万円 |
| 一周忌〜三回忌 | 3万〜5万円 |
| 納骨・開眼供養 | 3万〜10万円 |
| お盆・お彼岸の読経 | 5千〜1万円 |
| 戒名のみ(生前) | 10万〜30万円(院号などで変動) |
※地方や宗派、檀家としての関係性によって金額は変わります。
不安な場合は、遠慮なくお寺に直接「どのくらい包めばよろしいでしょうか?」と相談するのが安心です。
ほとんどのお寺は丁寧に教えてくれますし、失礼にはなりません。
近年はお墓を閉める墓じまいもありますが、これはお寺が管理していたり、管理者がいるところがありますので、まちまちです。
具体的にはそこの管理してるところに確認してみましょう。
お布施の包み方・封筒の書き方
お布施には、白無地の封筒または「お布施」と書かれた専用の奉書紙・のし袋を使用します。水引は基本的に「なし」が正式です。
表書きの書き方:
- 表面中央:「お布施」(濃い墨で縦書き)
- 下段(送り主):施主のフルネームを記載(◯◯家でもOK)
※法事の際は「御経料」「御法礼」と書く場合もありますが、「お布施」が最も一般的です。
中包み(内袋)がある場合:
- 表面:金額を「金〇万円」と漢数字で記載
- 裏面:住所・氏名を記入
例:金参萬円
漢数字の書き方については香典の正しい書き方に掲載してますので、ご参照ください。
お布施の渡し方とタイミング
お布施は、直接手渡しするのではなく「切手盆(きってぼん)」や小さなお盆に乗せて丁寧に渡すのがマナーです。
ただし、現代では白封筒に入れたものを丁寧に両手でお渡しすれば、形式にこだわらずとも失礼にはあたりません。
渡すタイミング:
- 葬儀:葬儀の際は一般的には葬儀が終わった一番最後にお渡しすることが多いです。
また、地域のお寺によっては寺参りという習慣もあり、その時にお渡しすることがあります。
次に近年は式の中で初七日をしたりすることもあり、お葬式の前にお渡しすることもあります。
※葬儀の場合は、僧侶やご葬儀のスタッフにご相談ください - 法事:僧侶が到着された際 or 読経後のご挨拶時に
- 自宅で読経:僧侶の退席前に、静かな場で丁寧に
「お車代」「御膳料」も忘れずに
遠方から来ていただいた場合や、食事の席を設けない場合などには、次のような謝礼も添えるのが一般的です。
- お車代:交通費の意味。5千円〜1万円程度。
- 御膳料:食事を用意できない代わりの謝礼。5千円〜1万円程度。
これらは「お布施」とは別封筒に包み、それぞれ「お車代」「御膳料」と表書きをし、僧侶に渡します。
よくある質問(Q&A)
Q:葬儀会社を通した時でもお布施は必要?
はい。葬儀社が僧侶の手配をしても、お布施は別途必要になることが多いです。中には「定額プラン」でお布施込みの場合もあるので、事前確認しましょう。
Q:現金以外でも渡していいの?
基本は現金です。
近年では「電子マネーや振込で」と希望される寺院も一部存在します。ただし、必ず事前に相談を。
私自身はこのケースがありませんでした。
Q:何か品物を添えるべき?
絶対ではありませんが、一般的には返礼品や引物(お茶などが多い)をお渡しすることが多いです。
まとめ:お布施は“感謝”の表現、迷ったら丁寧に尋ねよう
お布施に「正解」はありませんが、「不安」や「マナー違反だったらどうしよう…」と悩む方は多いもの。
しかし本来、お布施は「心を込めて施すもの」であり、形式ばかりにこだわる必要はありません。
一番大切なのは、お寺や僧侶への感謝の気持ちです。
わからないことがあれば、遠慮せずに直接相談しながら、丁寧に準備していきましょう。

昔とは違い、お寺も明確化されるようになっていると思います。
尋ねることが失礼ではありませんので、どんどんわからないことは尋ねて下さい。
お客様の中にはお寺もビジネスと考える人もいたくらいです。
不透明より明確化した方が安心ですよね!
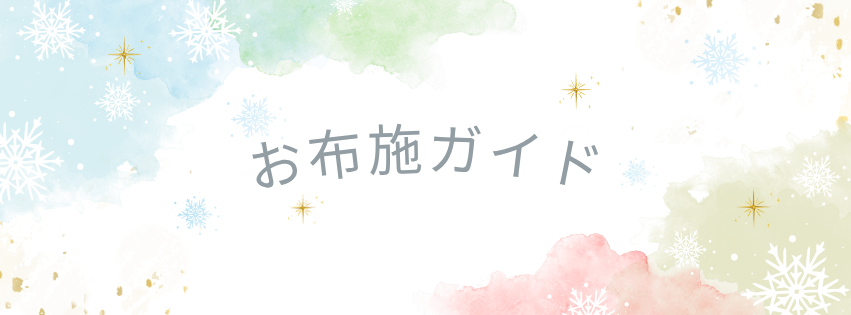
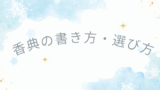
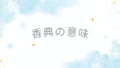
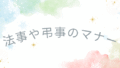
コメント