今回は香典返しの実務を担当してる立場から香典のお返しはどのような工程でされてるかです。
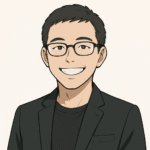
この人どんな人?と思われた方はたいした経歴ではありませんし、お恥ずかしい限りですが
プロフィールをご一読下さい。
香典の考え方:助け合いの心
葬儀を行う場合、考えなくていけないのは受付です。
昨今、家族葬が主流になり、一般会葬者も減りました。
当然、親族・身内だけの方もいるでしょう。
お返しが面倒だからなど仰られる方もおりました。
受付さえ、必要のないご家族もおります。
しかし、本来香典は助け合いの意味を持ちます。
葬儀にかかる費用は高額です。私自身は最後のお見送りに費用がかかってしまうのは当然と考えます。
車を購入する場合、一般的には時間をかけて検討してから購入しますよね?
しかし、葬儀はほぼ1日内でプラン(契約)を立てないといけません。それも、精神状態が良くない状況で…
そういう意味で香典を受け取るということは当然なのかもしれません。
香典をいただくことについてはこちらから
香典の受け取り方:3つのタイミング
香典をいただく場合、3ケースあります。
香典返しの二つの方法
香典の受け取りは大半受付時です。
受付をする場合、香典辞退を除けば二つあります。
当日返し・即返しとは
近年、葬儀社が勧めてくるのは当日返し・即返しです。
こちらの当日返し・即返しは地域によって呼び方が違うかも知れませんが、その場でお返しすることを指します。
当日返し・即返しの方法は二つあります。
◯一種返しは基本、3,000円や5,000円をメインとし、その場で香典返しをする方法です。
また、親戚など高額の方は改めて後日お返ししていきます。
メリットは香典を持ってこられた方、全てに渡すだけで良いことです。
デメリットは高額の方は改めてお返しをする必要がある。二度手間になる。
◯金額別返しについては、全金額に対して、準備してしまいますので、全ての方を対象にお返しします。
メリットは葬儀までにお返しができること。
デメリットは受付の際に、香典の中身を確認しなければいけないこと。(金額にあわせてなので)
後返しとは
通夜・葬儀では香典返しをせず、改めて忌明けを目処にお返しします。
メリットは当日バタバタしたり、香典のお返しの品物の不足を防ぎます。
葬儀が終わって少し落ち着いたら準備ができます。また、人によってお返しを変えることも可能です。
デメリットはいただいた方のリストアップです。
これが結構大変と思い、香典を辞退をする方もおります。
ただし、葬儀社によっては葬儀の後のお手伝いをする係がいるところもあります。
事前に相談できるようであれば、葬儀社に伺ってみましょう。
関連記事はこちら👉 : 香典返しの基本と豆知識
後返しを郵送する場合の注意点
さて、本題はここからです。
現在、私はこのお仕事をいただいてます。
香典のお返しは近所の方に持って行く場合は、お客様にてお持ちするのがよろしいです。
ただ、その方のお勤め上、お持ちするタイミングがないようであれば、郵送も考えましょう。
後返しの送る期日
葬儀後に役所の手続き、家の片付け、お寺様へご挨拶、位牌や仏壇の準備など、葬儀が終わっても忙しなく動かなければいけません。
当然、香典をいただいたら、お返しをしなければなりません。
一般的に香典のお返しは忌明けを目安にすることが多いです。
忌明けとは、四十九日法要・満中陰法要(浄土真宗では三十五日法要)を指します。
発送の準備を考えると一週間から10日は日数を要すこともありますので、余裕があるときにリストアップします。
また改めて、忌明けまでに何をしたらよいかなども記事にさせていただければと思います。
香典返しの金額目安
これは地域によります。
一般的には半返しと考えられます。私の地域はこちらです。
また、3割返しもあります。
葬儀社に聞いてみるといいです。
半返し?3割返し?とは…
例えば、1万円の香典をいただいたら、半返しは5千円ほどのもの、3割返しは3千円ほどのもととお考えください。
関連記事はこちら👉 :香典はいくら包んだらいい?香典はいくらが正解?
供花・供物をいただいた場合の対応
供花や供物をいただいた、それはどうしたら?と聞かれることがあります。
基本的には必要ないものだとは考えますが、香典をいただいた場合、少しお気持ちプラスするといいです。
香典返しに添える挨拶状
さて、〇〇様に5000円のカタログギフトを送ることに決めたとします。
でも、そのまま送っていいのか?と思う方もいるでしょう。
香典を郵送でお返しする場合、つけるべきものは挨拶状です。
挨拶状の一般的な文面は👇👇
法名 〇〇院釋〇〇 忌明志 ⬜︎⬜︎家
このたびは、故◯◯◯◯(続柄・名前)の葬儀に際しまして
ご丁重なご香典、ご厚志を賜り、心より御礼申し上げます。
おかげさまで忌明け法要にあたり滞りなく相済ませることができました。
ここに生前のご厚情に深く感謝申し上げるとともに、
供養のしるしとして心ばかりの品をお届けさせていただきます。
本来であれば拝趨のうえお礼申し上げるべきところ、
略儀ながら書中にてご挨拶申し上げます。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
令和○年○月
喪主 ◯◯◯◯
住所 ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
このような挨拶状をお入れします。
本来であれば、挨拶をしてお渡しすることを想定しますが、郵送の場合はお品物とは別に準備が必要になります。
この挨拶状は香典返しをする会社・デパート等によって異なりますので、そちらも✅要チェックです。
法名や戒名を入れたり、文章を変えたりすることもできますので、チェックしてみましょう。
発送の流れと裏方の仕事
こうして、ようやく準備ができ、発送させていただきます。
私どもはその間、下記のような作業工程をしております。👇
- リストのチェック
(手書きの場合、住所が途中までになってないかなどたくさんのことを確認します。) - 品物の取り寄せ(商品によっては在庫がありませんので、取り寄せします。)お菓子・食品系
- 挨拶状の作成(定型文ではありますが、戒名法名・住所・喪主名など、要チェックです。)
- 作業・包装(品物に挨拶状をお入れして、包装します)
- 発送の準備
(リストを元に発送の準備を行います。人が作業するものなので、Wチェックなどしてます。)
簡単そうに見えて、私的には結構大変な作業工程です。もちろん、1人で全て行ってはおりません。
【まとめ】香典返しは「感謝」を伝える大切な行為
香典返しは、単なる形式的なお返しではなく、
故人を見送るにあたり支えてくださった方々への「感謝の気持ち」を伝える大切な機会です。
葬儀直後は心身ともに負担が大きく、香典返しまで手が回らないことも多いもの。
ですが、少しずつ落ち着いてきたら、故人の代わりに丁寧な挨拶とお礼をお届けすることで、
ご縁のある方々とのつながりを守ることにもなります。
地域や家族の事情に応じて無理なく、けれど誠意をもって対応できるよう、
この記事が参考になれば幸いです。
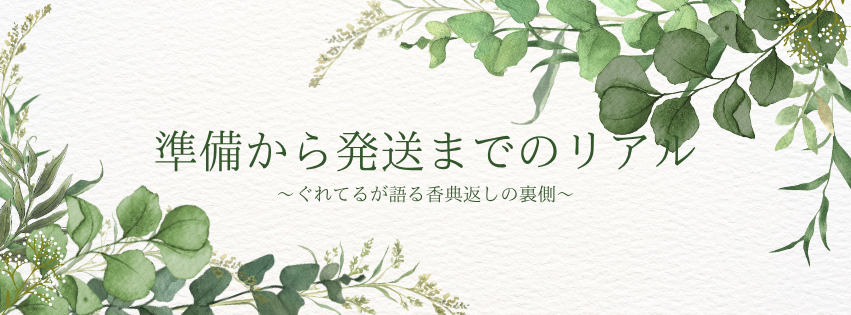

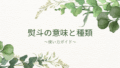
コメント