法事は、亡くなった方の冥福を祈り、供養の気持ちを表す大切な儀式です。
しかし、いざ自分が施主(主催者)や参加者になると、「何を準備すればいいの?」「服装は?」「お布施ってどうすればいいの?」といった疑問が次々と浮かんでくるものです。
この記事では、法事の基本から具体的な準備、マナー、さらにはよくある質問まで、分かりやすく解説します。
初めての方でも安心して準備できるよう、実例を交えながらご紹介します。
そもそも法事とは?
法事とは、故人の命日に合わせて行う仏教の供養の行事のこと。
代表的なものに「初七日」「四十九日」「一周忌」「三回忌」「七回忌」などがあります。
法要(お経を読む宗教儀式)と、その後の会食や返礼などを含めた一連の流れを「法事」と呼びます。
余談
「3」や「7」の年忌が多い理由とは?
年忌法要では、三回忌・七回忌・十三回忌など、「3」や「7」がつく年が多く選ばれていることにお気づきでしょうか? 実はこれ、古代インドや中国の思想、そして仏教的な意味合いが深く関係していると言われています。
まず、「7」について。インドでは昔から“7日”という区切りが大切にされてきました。日本の「初七日」「四十九日」などの法要も、こうしたインドの文化や仏教の考えが元になっています。さらに、中国の道教では「三魂七魄(さんこん・ななはく)」という、人の魂の構造を表す思想があり、「7」には人間の命の成り立ちを表す深い意味があるとされていました。
仏教においても、「7」には特別な意味があります。たとえば、お釈迦さまが誕生したときに七歩歩いたという有名な伝説がありますが、これは「人の迷いである六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)を超えて、悟りに至る」という象徴でもあるのです。
では「3」にはどんな意味があるのでしょうか?
仏教では「2」が対立する二元論、たとえば「損か得か」「勝ちか負けか」など偏った見方を表すとされます。その「2」を超える「3」には、物事をバランスよく捉え、偏見から離れるという意味が込められていると言われています。
このように、「3」や「7」という数字には、それぞれ仏教的な哲学が深く根ざしています。年忌法要の年数がこれらの数字に沿って組まれているのも、単なる偶然ではなさそうですね。
ちなみに、十三回忌や二十五回忌も意味がないわけではありません。日本では古くから十二支の巡りが重視されており、十二年で一巡、二十四年で二巡します。十三回忌や二十五回忌は、こうした干支の節目に合わせて行うという文化的背景があるとも言われています。
さらに、五十回忌については、仏教だけでなく神道の影響も見逃せません。神道では、亡くなってから50年がひとつの区切りとされ、「弔い上げ」という最終的な儀式が行われることがあります。仏教にもこの考えが影響し、五十回忌を最後の大きな法要として行う慣習が根付いているのです。
このような背景を知っていると、年忌法要の意味がより深く理解できますし、回忌の節目を迎えるご家族や親族との関わりも、いっそう大切に思えるのではないでしょうか。
法事の主な準備とは?
服装マナー
参列者も施主も、基本的には黒の喪服を着用します。女性はワンピースやアンサンブルスーツ、男性はブラックスーツが一般的です。ただし、三回忌以降になると「略喪服(ダークスーツなど)」でも問題ない場合があります。
小さなお子さんを連れて参列する場合は、子供も落ち着いた色味の服装を選びましょう。
お布施の金額と渡し方
僧侶へのお布施の目安は、
- 四十九日法要:3万〜5万円
- 一周忌以降:2万〜5万円
- お車代(遠方から来てもらう場合):5千〜1万円
- 御膳料(会食を辞退された場合):5千〜1万円
渡す際は白無地の封筒または「御布施」と書かれた専用袋に入れ、ふくさに包んで渡します。手渡しする際には一言感謝の言葉を添えるのが丁寧です。
よくあるQ&A
Q:法事の料理はどこまで準備すべき? A:家族のみの法事では仕出し料理で十分です。規模が大きい場合は料理店や会場を借りるケースもあります。
Q:案内状はいつ出すべき? A:法要日の1ヶ月前を目安に出しましょう。返信の締切は2週間前が目安です。
Q:人数が少なくても引き出物は必要? A:家族だけでも引き出物は用意するのが一般的です。
最近はカタログギフトやお菓子の詰め合わせなどが人気です。
宗派や地域による違いも確認を
浄土真宗、曹洞宗、真言宗など、宗派によって法要の意味や進行、準備物が異なる場合があります。たとえば、真宗では「お供えを供えること」よりも「仏縁に遇うこと」に重きを置くことも。
また、関東と関西でもマナーや食事内容、会食の習慣などに差があるため、親族に相談したり、地域の葬儀社やお寺に確認しておくと安心です。
まとめ:大切なのは「心を込めること」
法事は形式にこだわるだけでなく、故人を想い、家族や親族と心を通わせる場です。
「正解」が一つではないからこそ、自分たちに合ったスタイルを選びましょう。
迷ったら、菩提寺や葬儀社に相談するのも一つの手です。
大切なのは、故人への感謝と敬意の気持ちを忘れないことです。
法事は故人を偲び、家族や親族が集まる貴重な時間でもあります。形式にとらわれすぎず、感謝の気持ちを大切にしながら、心を込めた法事を行いましょう。
また仏縁と仏教(お釈迦さま)の教えに出会うこと、仏壇・ご先祖に手をあわせることでもありますが、
個人的にはお釈迦さまの御弟子になられた故人の元に集まられた遺族親族の集まりも縁だと考えます。
せっかくのご縁で皆様の繋がりがありますので、頂いたご縁は大切に感じながらお過ごしいただくとよろしいと思います。
関連リンクでさらに詳しく

今回は余談が大きくなってしまいました。
知らないことを知ることって楽しいですよね。
私自身も書きながら勉強させていただいてます。
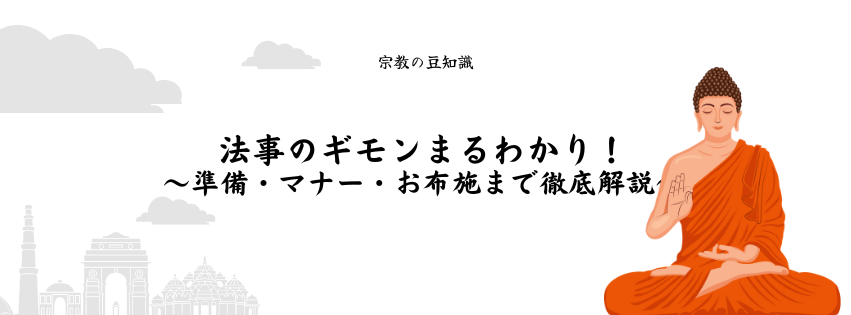
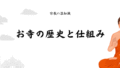
コメント