贈答のシーンでよく目にする「熨斗(のし)」。けれど、「なんとなく付けているけど、正直意味はよく知らない…」「水引との違いは?」「どの場面にどれを使えばいいの?」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、熨斗の意味や種類、場面別の使い分けを徹底的に解説します。あわせて、熨斗とセットで用いられる「水引(みずひき)」や表書きとの関係も紹介し、贈り物で失礼がないようにするための完全ガイドとしてお届けします。
熨斗(のし)とは何か?:その起源と意味
熨斗とは、元々は「熨斗鮑(のしあわび)」という長寿や健康を祈る縁起物が由来です。昔は実際に乾燥した鮑を薄く伸ばしたものを贈り物に添えていましたが、現代ではその象徴として「のし紙」や印刷された「のし飾り」が使われています。
熨斗の目的:
- 贈り物を“改まったもの”として格式を高める
- 相手に対しての敬意や祝意を表す
注意点として、仏事(弔事)では熨斗を使いません。熨斗は慶事用であり、お悔やみや法要では“熨斗なし”が基本です。
熨斗の構成要素:のし紙・水引・表書き
熨斗は一般的に以下の3つの要素で構成されます。
- のし(飾り):右上に印刷されている飾り(慶事用)
- 水引:中央の帯状の結び紐(用途によって色や結び方が異なる)
- 表書き:「御祝」「内祝」「御供」など贈り物の目的を示す文字
熨斗の種類と使い分け(シーン別)
1. 結婚祝い・出産祝い・新築祝いなどの慶事
- 熨斗あり、水引:紅白の結び切り(または蝶結び)
- 表書き例:御祝、御結婚御祝、内祝
※「結び切り」は一度きりであってほしいお祝い(結婚など)、「蝶結び」は何度あってもよいお祝い(出産や進学)に用います。
2. お中元・お歳暮などの季節の贈り物
- 熨斗あり、水引:紅白の蝶結び
- 表書き例:御中元、御歳暮、御礼
3. お見舞い・快気祝い
- お見舞い:熨斗なし、水引:紅白の結び切り、表書きは「お見舞い」
- 快気祝い:熨斗あり、水引:紅白の結び切り、表書きは「快気祝」
4. 法事・弔問・香典返し
- 熨斗なし、水引:白黒または双銀の結び切り
- 表書き例:御供、志、御仏前
弔事では熨斗は絶対に付けないよう注意してください。
熨斗紙の選び方:印刷の有無やサイズ
印刷のし紙と短冊のし
- 印刷のし紙:贈答品の包装紙に直接のしの印刷があるもの。大量の贈り物に便利。
- 短冊のし:小さな贈り物や返礼品に用いる簡略タイプ。最近はこの形式も多く見られます。
名前の書き方
- 表書きの下に贈り主の名前を記入。
- 個人ならフルネーム、連名なら右から年長者や目上の人を先に記載します。
- 会社名+代表者名で記載する場合もあり。
【関連記事】 👉 感謝を伝える贈り物の選び方(法要・お供え編)
熨斗を使うときの注意点まとめ
| シーン | 熨斗の有無 | 水引の種類 | 表書き例 |
|---|---|---|---|
| 結婚祝い | あり | 紅白・結び切り | 御結婚御祝 |
| 出産・進学祝い | あり | 紅白・蝶結び | 御祝、内祝 |
| お中元・お歳暮 | あり | 紅白・蝶結び | 御中元、御歳暮 |
| お見舞い | なし | 紅白・結び切り | お見舞い |
| 快気祝い | あり | 紅白・結び切り | 快気祝 |
| 法事・弔問 | なし | 白黒・結び切り | 御供、御仏前、志 |
おわりに:熨斗の意味を知ることは心遣いの第一歩
熨斗は単なる形式ではなく、日本人の心遣いや敬意を形にした文化の一部です。場面に応じて正しい熨斗と水引を使い分けることで、相手への気配りを表すことができます。
最近では、デジタルギフトや簡略化された贈答が増える一方で、こうした伝統的なマナーが改めて見直されています。熨斗の基本を知っておくことで、いざという時にも安心して対応できるでしょう。
\ あわせて読みたい! /
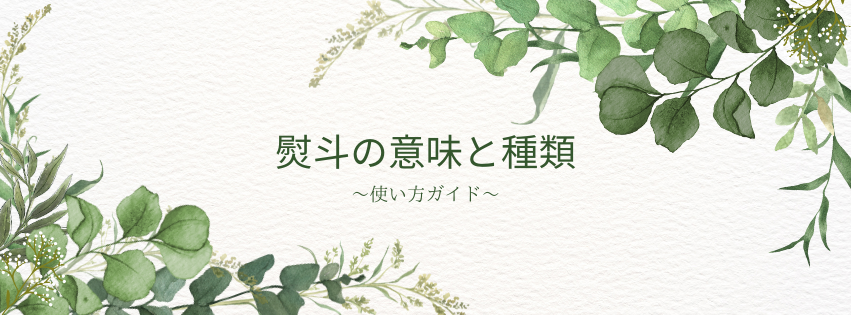


コメント