〜いざというときの「迷わない」ための備え〜
ある日突然、大切な家族が亡くなる―。
その瞬間から、ご遺族には「喪主としての責任」がのしかかります。
しかし実際は、ほとんどの方が喪主や葬儀の準備を経験したことがなく、何から手を付ければいいのか分からず混乱してしまいます。
この記事では、突然の訃報に備え、喪主や近しい家族が「すぐに動ける」ための実用的なチェックリストを時系列でまとめました。
悲しみに暮れる中でも、できるだけ冷静に行動できるよう、保存版としてお使いください。
訃報直後にやるべきこと【当日】
✔️1. 医師による死亡確認
病院であればその場で死亡診断書が発行されます。
自宅などで亡くなった場合は、かかりつけ医や救急に連絡します。
✔️2. 親族への第一報
「まず知らせるべき人」に優先的に連絡を。
- 家族・親戚(喪主が誰かを相談)
- 葬儀社(搬送・打合せの依頼)
- 菩提寺や宗教関係者(枕経や葬儀相談のため)
【ポイント】
この時点では「亡くなったことの報告」にとどめ、日程や詳細は決めずにおきます。
葬儀社と打ち合わせ【亡くなった当日〜翌日】
✔️3. 葬儀社との打ち合わせ
事前に決まった業者がなければ、地域で評判の良い葬儀社へ連絡。
以下を確認しておくとスムーズです。
- 葬儀の形式(家族葬/一般葬/直葬 など)
- 会場(自宅/葬儀会館)
- お布施や宗教者の手配
- 参列者の規模と席数
- 費用の概算(見積もりを出してもらう)
【ワンポイント】
喪主に決まった方が最終決定権を持つため、あらかじめ「どこまで任せるか」を家族で共有しておきましょう。
通夜・葬儀の準備【翌日〜3日後】
✔️4. 日程の確定と関係者への案内
会場の空き状況・僧侶の予定・家族の都合を調整し、葬儀日程を確定。
参列者に以下を伝えましょう。
- 通夜・葬儀の日程と場所
- 喪主の氏名と連絡先
- 服装(平服で可か、喪服か)
- 香典・供花の受付状況
✔️5. 会場や遺影・供物の準備
- お供え物や供花の希望をまとめる
- 遺影写真の選定と手配(できるだけ顔が正面で写ったもの)
- 火葬許可証・印鑑・保険証などの書類確認
【豆知識】
喪主が挨拶をする場面があるため、簡単な例文を用意しておくと安心です。
定型文を葬儀社が持っていることも多いかと思います。ありますか?と聞いてみてはいかがでしょうか。私はお客様にお渡しできるように準備しておりました。
通夜・葬儀当日の流れ
✔️6. 通夜の受付と式進行
- 受付係、香典係の手配
- 会場スタッフとの最終確認
- 喪主として焼香・挨拶(短くても問題なし)
✔️7. 葬儀当日〜火葬
- 出棺前の故人とのお別れ(柩の中に入れたいものなど *地域によって違うため、要確認)
- 火葬場への同行と骨上げ
- 精進落とし(葬儀後の会食)の手配と席順確認
【注意】
当日は感情のコントロールが難しくなりがちなので、無理に挨拶を完璧にしようとせず、「お気持ち」で十分です。
葬儀後に必要なこと
✔️8. 市区町村での手続き
- 戸籍抄本の発行
- 健康保険証の返納
- 年金停止の手続き *だいたい二週間ほど
✔️9. 香典返しと挨拶状の手配
- 即日返し or 後日(四十九日頃)で分ける
- 贈答マナーに合わせた水引・表書きを確認
🪙香典返しの相場や、適した品物については
👉 「香典返しの品選び早見表」 をご覧ください。
よくある質問とその対応
Q. 喪主は長男が必ずやるものですか?
A. 一般的には、故人の配偶者→長男→長女→次男…と続きますが、絶対ではありません。家族間での話し合いや事情(高齢・遠方・精神的に難しいなど)を踏まえ、柔軟に決めることが多いです。
Q. 服装や挨拶が不安です…
A. 喪主の服装は黒の礼服が基本です。挨拶は定型文でも問題ありません。葬儀社や僧侶が事前に文案を用意してくれることもあります。
Q. 失敗したらどうしよう…
A. 大丈夫です。ほとんどの方が喪主は初めてです。失敗を恐れるより、「できる範囲で精一杯つとめる」気持ちがなにより大切です。
心のケアと長期の備え
喪主という大役を終えた後、心身の疲れを感じる方も少なくありません。
故人を偲びながら、自分自身の終活にも目を向けるタイミングとして考えることもできます。
- エンディングノートを書き始めてみる
- 家族で終活について語り合う
- 葬儀を振り返って感じたことを記録しておく
👉 参考記事:はじめての終活ガイド:何から始めればいいの?
まとめ:喪主になっても「チェックリスト」が味方に
突然の訃報に直面したとき、深い悲しみと混乱の中でもやらなければならないことは山ほどあります。
そんなときこそ、「何をすればいいか」が整理されたリストがあれば、心強い支えになります。
今のうちに印刷しておいたり、家族で共有しておくことで、いざというときにも落ち着いて対応できるでしょう。
また、本記事のチェックリスト版PDFのご希望があれば、後日ご提供も検討しています。お気軽にご相談ください。
喪主になった時の備えは、自分と家族を守る行動です。
小さな準備が、大きな安心につながります。
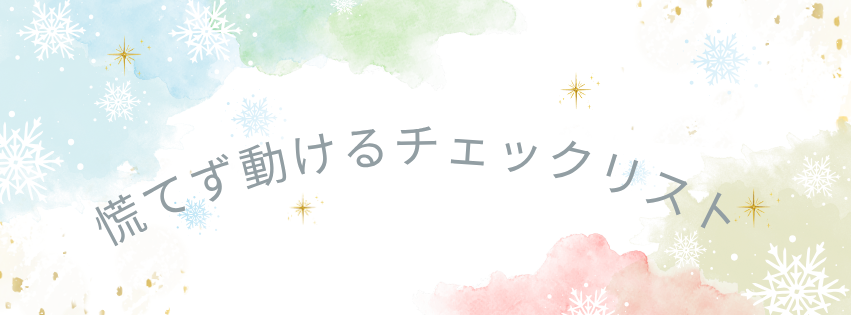
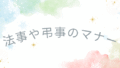
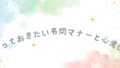
コメント